
道教は広くはタオイズムであるが、タオイズムそのものには、さまざまな観念技術も思想要素も多様になっている。そこには神仙道もあれば、導引術のような呼吸医術もあるし、呪術(方術・道術)もある。王羲之や竹林の七賢のような清談(せいだん)の趣向もまじっている。
ここに、「神仙タオイズム」と「陰陽タオイズム」という分け方ができる・・・
そういうタオイズムが、やがて五斗米道や全真教のような過激な成団道教の運動にもなっていった。そうなると、そこには老子の無為自然の思想から逸脱したものも少なくない。けれどもどんなに逸脱しても、道教は老子を忘れない。しばしば「黄老」と尊称して、黄帝と老子を同一視した。
それはすべての仏教がブッダを忘れないというような意味になっているかというと、また儒教が孔子を忘れないようになっているかというと、そうではない。
老子はロゴスの中心にはいない。そこが老子の不思議なのである・・・
その老子の不思議を実感するのには、なぜか時間がかかる。『老子』を読んだからといって、また読みこんだからといって、老子の不思議の正体はわからない。『老子』はわずか5000字あまりのテキストなのだから、読みこみに手間どるなどということはまずないのだが、そういうことでは伝わってこないものがある。
ふつう、老子の思想の根本は「道」と「無為」にあると思われている。まとめて「無為自然」ともいう。第1章の冒頭にして「道の道とすべきは常の道に非ず」とある。しかし、すぐに実感できるだろうが、老子はその説明が老子的なのである。
道の道とすべきは常の道にあらず。
名の名とすべきは常の名にあらず。
名なきは、探知の始めにして、名あるは万物の母なり。
故に、常に欲なきもの、以てその妙を観(見)、
常に欲あるもの、以てその、徼を観る。
この両(ふた)つのものは、同じきより出でたるも、
しかも名を異にす。同じきものはこれを玄という。
玄のまた玄、衆妙の門なり。【体道1】
すでに「道」とは何かということがプレゼンテーションされているのだが、その言いっぷりがはやくも老子なのである。それゆえ第1章で言っていることは、次のようなことになる。
もしもタオが語りうるものであれば、語りうるものなのだから不変なタオではない。
もともと名づけられるものなど、それは不変な名であるわけはない。
考えてみればわかるだろうけれど、そもそも天地が出現したのは「名づけえないもの」からである。
これが「無名」だが、無名がいっさいであるはずもない。いっさい以前だ。
むしろ「有名」こそが歴史上では万物の母なのである。
しかし、この無名と有名を同時の出来(しゅったい)として語るには、どうするか。
隠れた本来としての「妙」(=見えない本質)を、
そこから出た「徼」(きょう=ものごとの結果や端末)と一緒に見る必要がある。
どう一緒に見るかといえば、実は「妙」と「徼」とは同じ鋳型から発したものなのだと見るべきだ。
それは鍵と鍵穴の関係なのである。
その一緒に発するところをどうよぶかといえば、それをこそ「玄」と言いたい。
たんなる玄ではあるまい。「玄のまた玄、衆妙の門」ともいうべき本来の玄なのである。【体道1】
肝腎なところは、ひとつには「妙」と「徼」、「無」と「有」とは鍵と鍵穴のごとくの二項同体の発現(emergence)で、「道」を語るにはそのような見方を挟むことになると言っているということだ。もうひとつには、そのように言いうるということを含めて、このような見方は「玄」あるいは「玄のまた玄」にあるということだ。黒に染めていくときの漆黒の直前の色が玄である。これが短い第1章の文言が暗示していることなのだが、他の章にも似たような言い方は少なくない。
しかしそのどこにおいても、老子はひたすら暗示的なのである・・・
説明はしているが、いろいろな言い方をしながらも明確にしようとはしない。タオの捉えどころをあえて「玄のまた玄、衆妙の門」に戻してしまうのである。
たとえば第21章では、「道のものたる、これ恍、これ惚。その中に象あり、恍たり惚たり。その中に物あり、窈(よう)たり冥(めい)たり。その中に精あり、その精、甚だ真たり、信たり」というふうに。【異俗21】
これは、タオの姿はなんともぼんやりしていて、しかしそのなかに形象があり、その形象のなかに実体があるとしか言いようがないというのである。
この「恍惚」と「窈冥」(ようめい)が格別にいい・・・
なんとも渺々としている。タオは恍惚の内に「象」と「物」を秘め、窈冥のうちに「精・真・信」を秘めるのである。
それを第14章ではさらに、「縄々(じょうじょう)として名づくべからず、無物に復帰す。これを無状の状、無物の象という」とも言った。【賛玄14】
無名であって有名、「妙」であって「徼」、そして恍惚であって窈冥。それらを同時に孕んでいる「玄なるもの」がタオなのだ。けれどもそのタオから「象」も「物」も「精・真・信」も出る。出るのだが、この出るは派生ではない。
“復帰”なのである・・・
そこへ戻って帰っていく“復帰”なのである。老子を“復帰の思想者”と言ってもいいほどだ。したがって、いまあげた数々の「象・物・精・真・信」はたんなるコンセプトなのではなく、タオがもたらす「一なるもの」の属性だったのである。
老子にはけっこう知覚についての言及が多い。老子の「知覚の現象学」とさえいえる。その「知覚の現象学」のひとつにタオを説明するにあたって、老子はしばしば「希」「夷」「微」を持ち出している。「希」は聴覚的なもので、タオは聴けども聞こえずの希であり、「夷」は視れども見えずの夷で、「微」は搏(とら)うれども得ずの微である。
このような説明をつかって、老子はタオが知覚のうえでも微妙きわまりない超感覚的なものであることを暗示する。
しかし、そのうえでとたんにもちこむのが「一」だったのである・・・
そこが大変なのである。
「之を視れども見えざる、名づけて夷という。之を聴けども聞こえざる、名づけて希という。之を搏うれども得ざる、名づけて微という。この三つのものは、詰(きつ)を致すべからず。故に混じて一と為る」【賛玄14】
聴覚でも視覚でも触覚でもつかめないのだから、これらが不思議に混じって「一」となっているのがタオなのだ。老子は、そのように知覚がとらえきれないものを「一」にする。ここにおいて、タオは「無状の状、無物の象」としての「一」になっていく。こうなると、「一」は未詳に発生するもののすべてをあらわすものとなる。
その「一」に老子は“復帰”する・・・
第39章には、このようにある。
すでに「一」を獲得したもののなかでは、天は一ゆえに「清」であり、地は一ゆえに「寧」であり、神々は一ゆえに「霊」なのだ。また谷は一ゆえに「盈」(えい=満ちる)で、万物は「生」であり、侯王は「貞」なのだ。【法本39】
「一」は老子にとってはすべての資源の原器なのである。OSなのだ・・・
その原器は天・地・神・谷に漲(みなぎ)っている。そのエネルギーが「清・寧・霊・盈」であり、それを受けて万物は「生」を躍らせ、人間社会のリーダーたちは一を得て「貞」(かしら)になる。しかし「一」がなければ何もおこらない。「一」に戻らなければ、何も始まらない。ちなみに「清・寧・霊・盈・生・貞」はセイ・ネイ・レイ・エイ・セイ・テイというふうに、韻も踏む(こういう韻による語句の選定はしょっちゅうのことだ)。
こうして、よく知られてきた「道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生ず。というフレーズが大声で鳴り、「万物は陰を負うて、而うして陽を抱く。沖気(ちゅうき)は以て和を為す」【道化42】というふうになる。
これは、道が陰陽の二気を生み、そこに沖気が加わって万物が化生するという、のちに“タオ原理”のように言われることになる老子の万物生成論である。むろん荘子にもあてはまるもので、つまりは“老荘思想の原理”でもあるだが、方程式ふうにいえば、道が無で、一二が陰陽の有で、三が沖気を和した有だということになる。「沖」とは渾然とさせるものをいう。では、このような「道」と「柔弱」とはどのような関係で響きあうものなのか。
「反は道の動、弱は道の用。天下の万物は有より生じ、有は無より生ず」【去用40】
根源に立ち返るということが「道」のいとなみであって、柔弱ということが「道」のはたらきなのである。この世界のすべては「有」という天地陰陽の気から生じるが、その有は「道」にひそむ無から生まれている。そういう意味だ。
「動」「用」が韻を踏んでいる。タオなるものは、そこへ戻ろうとするものに動き、そのときにはたらく“弱さ”というものが、「有と無のあいだ」にわれわれを運ぶ。と老子はそう言っている。「反」と「弱」とがタオに至る最も重大な方法として浮上しているわけである。
反は道の動、弱は道の用・・・
こういう箇所もある。
「学を為せば日に増し、道を為せば日に損す。これを損し、また損して、以て無為に至る。無為にして為さざるなし」【忘知48】
知を修めなさい。しかしその一方で道を修めなさい。そうすれば余計なことがへっていく。それをさらにへらしてへらしていけば、無為の境地というものがやってくる。そのほうがかえっていっさいを為すことが可能になるはずだ。
ところで第10章、20章、28章、55章に、すこぶる興味深い暗示的存在が出てくる。いやキャラクターといえばいいか、それとも存在象徴といえばいいか。それは“嬰児”というものだ。
「営魂(えいはく)に載(の)りて一を抱き、よく離るることなからんか。気を専らにして柔を致(きわ)めて、よく嬰児たらんか」【能為10】
「我、独り泊(はく)としてそれ未だ兆さず、嬰児の未だ孩(わら)わざるが如し」【異俗20】
「その雄を知りて、その雌を守れば、天下の谿(たに)と為る。天下の谿と為れば、常徳離れず、嬰児に復帰す」【反朴28】
「徳を含むことの厚きは、赤子(せきし)に比す」【玄符55】
これらがその箇所なのだが、これで一目瞭然、あきらかなように、老子の「反弱の存在」とは実は嬰児なのである。みどり児なのだ。
「柔弱なること、嬰児なるが如し」ということなのだ・・・
いいかえれば、老子のフラジャイルな存在学やナイーブ・オントロジーは「幼弱なるものの存在学」なのである。とくに嬰児が秘める当初の「孩(わら)い」(無垢なる笑い)に着目して、その嬰孩性(えいがいせい)をもってその存在学の始発とした。
この幼弱なる嬰孩性は、同時に「水のようなるもの」とイメージの裡でも重なってもいる。嬰孩性は「上善若水」であり、ということは、これは「道」の始発のイメージであって、かつまた最も至達したるものなのである。のちの明末清初に、王陽明をさらに独自に深化させた李卓吾が「童子」(赤子)を持ち出していたことが思いあわされる。
さて、最後に老子の国家論や組織論、つまり、「老子の統治(ガバナンス)論」について、ふれておく。ただし断っておくが、老子の国家や組織とは村落共同体のようなライトサイズの「小国」のことをいう。大国はハナから相手にしていない。なぜなら大国は小国を併合したり乗っ取る(take over)だけなのだから、すべての基本は小国にあるというのだ。
それならば、「無為を為せば、すなわち治なざることなし」【安民3】
老子の統治論の基本は「小国寡民」にある。国を小さくし、民も少なくして、文明の利器に頼ることなく、みんなが生命を尊ぶようになれば、そこから移住していく者もへるだろう。この基本方針だ。
「小国寡民。人に什伯の器あるも用いざらしめ、民をして死を重んじて遠く徒(うつ)らざらしむ」【独立80】
これは理想だ。問題は、そういう理想に近づけるにはどうするかということだが、老子はその方法についてはかなり一貫したことを提示している。
最も老子っぽい説明は第63章にある。
「無為を為し、無事を事とし、無味を味わう。小を大とし、少を多とし、怨みに報ゆるに徳を以てす。難をその易に図り、大をその細に為す。天下の難事は、必ず易より作(おこ)り、天下の大事は必ず細より作(おこ)る」【恩始63】
ここで「小を大とし、少を多とする」と言い、「難をその易に図り、大をその細に為す」と言っているのが、すばらしい。小こそが大であり、少こそが多なのである。そのうえで天下の難事はそれが易しいうちに手がけ、天下の大事に向かうときはそれを細かいところから取り組みなさいというのである。
よく老子の思想は無為自然で「無心」を勧めているのだから、「無欲」に徹することこそ統治の理念だろうと言われるが、日本人はそこに気をとられすぎている。それは老子独特の表現で、過剰な作為や過度の執着を戒めたと見たほうがいい。
それが「無為を為し、無事を事とする」ということなのである・・・
だいたい老子は逆説を好んだ。そのわかりやすい言いっぷりが、第18章、19章にあらわれる。ここには尋常な「無心」や「無欲」は憚らない。
「大道廃れて仁義あり。智慧出でて大偽あり。六親(りくしん)和せずして孝慈あり。国家昏乱して忠臣あり」【俗薄18】
「聖を絶ち智を棄つれば、民の利は百倍す。仁を絶ち義を棄つれば、民は孝慈に復す。功を絶ち利を棄つれば、盗賊のあることなし。素を見(あらわ)し、樸(ぼく)を抱き、私を少なくして欲を寡(すくな)くす」【還淳19】
大道が廃れたというのは、タオがもたらす無為自然な雰囲気がなくなってしまったということなのである。だからわざわざ仁義を持ち出したり、知恵をめぐらす必要がありすぎるようになって、親子兄弟夫婦の六親は和めず、私こそが忠臣ですというような連中が出てくる。
ここはいったん「聖」や「仁」や「義」を捨てて、「素」や「樸」に戻ってはどうか。そうでなければ混乱した時世のなか、本当の仁義も忠臣も見えてきっこない。そう、言うのだ。「樸」は「あらき」(何も加工されていない木々の状態)のことをいう。つまり老子は、リーダーという者たちがたいてい身勝手と横暴で失敗すると見ているわけなのだ。
それゆえこれを削(そ)がせることを、しきりに提示した・・・
そこに、リーダーがついついポピュリズムに乗りすぎることも見て取っていた。そのことが第53章に、大道のタオは平坦なものなのに、民衆というのはやたらに起伏や奇矯ばかりを好むので(マスメディアもそうなるが)、そこを注意しなさいと戒めるたことにつながっている。
それが、「大道ははなはだ夷(たいら)かなるに、民は径を好む」【益証53】なのである。
それなら老子はリーダーではなかったのか。いわゆる指導者ではなかった。老子自身は、みずから“三宝”と名付けた自戒をもっていた。「慈」「倹」「後」である。
「我に三宝あり。持してこれを保つ。一に曰く慈、二に曰く倹、三に曰く敢て天下の先と為らず、と」【三宝67】
慈悲をもつように努力し、できるかぎり倹約に徹して、天下の先に立つことをしないようにすること、これが老子の三宝なのである。しかし、世の中のリーダーはそうはいかないだろう。少なくとも先に立つ必要がある。ではどうするか。
そこで老子は「和光同塵」してみなさいというのだ・・・
これがまたまた、すばらしい。もともとの文章は次のようになっている。
「道は沖(むな)しけれども、これを用いて或(ひさし)く盈(み)たず、淵(えん)として万物の宗(そう)に似たり。その鋭(えい)を挫(くじ)き、その紛(ふん)を解き、その光を和(やわ)らげ、その塵を同じくす。湛として或(つね)に存するに似たり」【無源4】
これが「和光同塵」の原典だが、その説くところこそ、すばらしいガバナンス論である。次のような意味と思えばいいだろう。
道(タオ)は一見、空虚な器のように感じるかもしけないけれど、そうではなく、そこに何を入れても満ちるということがなく、万物の原器のようなものになっているものなのだ。なぜそんなことがおこりうるかというと、これを律するに、つねに鋭いものをなくし、紛(もつ)れているものをほぐし、すべてを光にまぜて和らげ、さまざまな塵と同化するようにしているからなのである。鋭利に対しては柔弱に、紛争に対しては奔放に、万事を光と塵とがまざるようにすることだ。これが原意だが、そこからリーダーたるものは、「挫鋭解紛・和光同塵」してみなさいというふうになる。ちなみに「紛」と「塵」が韻を踏む。
この第4章をさらに発展させたものが第56章にある。
「知る者は言わず、言う者は知らず。その兌(あな)を塞ぎ、その門を閉ざし、その鋭を挫き、その紛を解き、その光を和らげ、その塵を同じくす。これを玄同という。故に得て親しむべからず、得て疎んずべからず、得て利すべからず、得て害すべからず、得て貴ぶべからず、得て賎しむべからず。故に天下の貴となる」【玄徳56】
深く分かっている者はやたらに言辞を弄ばない。何かが言いたくなれば、そのよってきたる鍵と鍵穴に注目し、それによって気負いを挫き、気負いによる紛争を解き、自身の輝きすぎるところを和らげて、むしろ光と塵との差別がないほうに、自身をはこぶのである。
これが玄妙な合一というものだ・・・
こういうふうに言いながら、老子の統治(ガバナンス)論は信じがたいほど深遠なほうに向かっていく。老子を今日の言葉になおすという作業は、すでに多くの試みがあるので心配はない。
しかし、日本では老子はしばしば安岡正篤ふうな講義が流行していて、それこそ政治哲学に流用されてきたのだが、これに代わる老子講義が一般向けにもリーダー向けにも新たに待望されている。
【 編集後記 】:老子『道徳経(タオ・テ・チン)』
聖書の次に世界中で最も多く翻訳されている智恵の書・・・『道徳経(タオ・テ・チン)』。
『老子』『荘子』『周易』は三玄と呼ばれ、これをもとにした学問は『玄学』と呼ばれた・・・。
道家の祖「老子」が残した書は、実は現代に流布されている分量(81章)の三分の一が真実であり、さらに「仮字」を応用した『緻密な二重構造の仕掛け』で、秘儀が封印されている。
老子書は本来、『陰(裏の意=秘儀)』と『陽(表の意=実践的哲理)』を合わせて、老子の言わんとする真意は語られるのである。
今や西洋社会でも最もよく知られた東洋の賢者の老子を、人々は表層の意味でしか理解しておらず、中国人や道家の人々さえもその真実を知る者は皆無に等しい・・・。
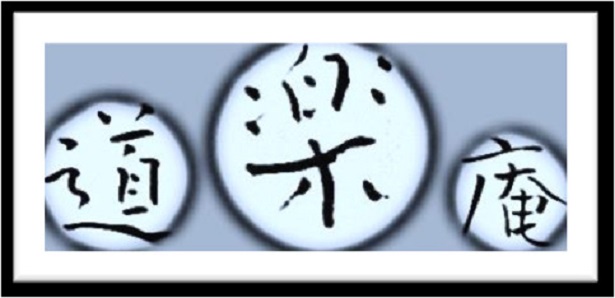







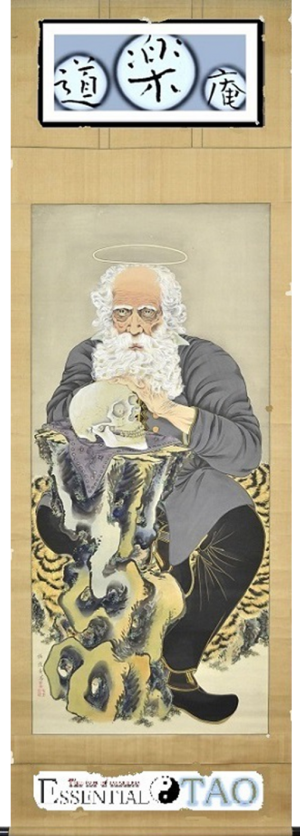

コメントはこちら